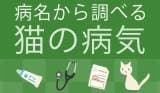要因
猫の尿石の要因はほとんど食事にあると考えられています。正常な尿ph(ペーハー)は弱酸性のph6〜6.5ですが、この数値にphを維持できるキャットフードは市販のものでは案外少ないです。
猫缶や煮干、かまぼこ、海苔などのおやつが要因になることもあります。
種類
尿石はいくつかの種類があり、原因や尿石のある場所、治療方法は種類によって異なります。
- 1.ストルバイト
-
尿石の成分 ストルバイト(リン酸アンモニウムマグネシウム) 尿石のできる場所 膀胱など 特徴 アルカリ性の尿でできやすい 猫で最も多くみられる尿石です。できる原因としては、尿中のマグネシウムやアンモニウム・リン酸塩の濃度上昇、マグネシウムの過剰摂取、水分摂取量の減少などで、膀胱によくできます。オス猫では尿道につまって尿が出にくくなってしまうこと(尿道閉塞)があります。肥満の猫は尿石ができやすいようです。
- 2.シュウ酸カルシウム
-
尿石の成分 シュウ酸カルシウム 尿石のできる場所 膀胱、腎臓、尿管、尿道など 特徴 どのphの尿でも(アルカリ性〜酸性)できやすい 2番目に多くみられる尿石です。できる原因は不明なところが多く、マグネシウムの摂取制限、尿の酸性化、ナトリウムの過剰摂取、ビタミンB6欠乏などが考えられています。膀胱のほかに腎臓、尿管、尿道にも見られます。
- 3.その他の種類
- その他、シスチン、シリカなどの尿石もありますが、あまり見られません。
症状
症状は尿石のある場所によって異なります。
- 1.膀胱結石(膀胱にできる結石)
- 血尿、頻尿、細菌尿がよくみられ、排尿痛や排尿困難を起こすことがあります。
- 2.尿道結石(尿道にできる結石)
- 尿道閉塞によって排尿困難、頻尿、尿失禁などが見られます。尿道閉塞はオス猫に多く、完全につまってしまった場合膀胱がぱんぱんになり、2日以上放置すると尿毒症・急性腎不全を起こしてしまします。3日尿が出ないと死亡する確率が高くなりますので、尿が出てないと思われたら1日以内に病院へ連れていきましょう。
- 3.腎結石(腎臓にできる結石)
- 腎結石は無症状であることが多いようです。結石が大きくなることにより正常な部分が圧迫されて腎不全が起こったり、詰まると水腎症が起こります。
診断
- ・身体検査
- 触診によって尿道閉塞で膨らんだ膀胱、また水腎症により大きくなった腎臓が確認できます。
- ・尿検査
- 血尿、蛋白尿、結晶尿、細菌尿、尿pHを調べます。
尿中の結晶から尿石の種類を推定することができます。 - ・X線検査・超音波検査
- 尿石の存在を確認します。尿石は一般的にX線不透過性ですが、透過性の高い尿石や厚さの薄いものは確認が難しいです。
- ・血液検査
- 腎臓機能の状態などを調べます
治療
- 1.尿石の成分がストルバイトの場合
- 尿石の溶解を行います。溶解の基本は専用の食事(療法食)により尿中のアンモニウム、マグネシウム、リン酸の濃度を下げ、尿を酸性化することです。膀胱内尿石の溶解には1〜4ヶ月、腎結石ではそれ以上の期間が必要です。
尿石のある猫は膀胱炎になりますので抗生剤の投与も必要です。重度の尿石や、尿カテーテルで開通できない尿道閉塞の場合は手術が必要なこともあります。 - 2.尿石の成分がシュウ酸カルシウムの場合
- シュウ酸カルシウムは一度できてしまえば溶解しませんので、手術をして尿石を取り除く必要があります。
予防
・正常な尿(ph6〜6.5)を維持できるキャットフードを猫に与える
・水飲み場を増やし、水をたくさん飲ませる(成分の濃い尿は尿石ができやすいため)
しかしphが正常でも尿石症になる場合があります。