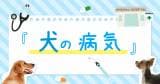犬の健康を守るために欠かせない、ワクチン。
でもワクチンについてはよくわからない…という方も多いのではないでしょうか。
今回は、そんなワクチンについて大特集!
なぜ子犬は何回もワクチンを打たなくてはならないのか、「混合ワクチン」とは何か、
そしてワクチンの副作用についても見ていきましょう。
1.ワクチンとは
病原体を無毒化して健康な犬に接種し、その病原体に対する免疫力を持たせることによって病気を防ぐというのがワクチンのしくみです。
病原体のように体内に侵入する異物を「抗原」といい、抗原に対抗するために体内で作られる物質を「抗体」といいます。生体は抗体を作ることにより、抗原に抵抗する力(免疫力)を持ちます。
<ワクチンの代表的なタイプ>
(1)不活化ワクチン
病気の抗原情報のみを注射するタイプ。狂犬病ワクチンは不活化ワクチンです。
(2) 生ワクチン
病原性を失くして無毒化した生きているウィルスを注射するタイプ。混合ワクチンは生ワクチンが主流です。
<混合ワクチンについて】
混合ワクチンは2種〜9種混合までさまざまです。
◆混合ワクチン(5種)
1.パルボウィルス …現在の日本ではこれらが頻発しますので、最低限このワクチンは必須です。
2.ジステンパーウィルス
3.伝染性肝炎 …まれに感染例がありますので、ここまでは欲しいところです。
4.アデノウィルス
5.パラインフルエンザウィルス
さらにレプトスピラ等何種類かを加えると、7種〜9種のワクチンになります。
多種のワクチンを打てば、それだけ多くの病気を防ぐことができる利点はありますが、数が増えるほど副作用が強く、元気・食欲の後退が見られます。実際に何種類の混合ワクチンを注射するかは、獣医さんと相談するとよいでしょう。
2.推奨ワクチンプログラム
子犬のワクチンは(一般的な回数として)3回は打つ必要があり、また適切な頻度で追加接種をしなくてはなりません。
人間のワクチンは1回でいいのに、どうして?と思う方もいるでしょう。ワクチンを何回も打つのには理由があります。子犬のワクチンを例に解説していきましょう。
ワクチンは病原体を無毒化して健康な犬に接種し、その病原体に対する免疫力を持たせることを目的とします。
ところが子犬の場合、母犬から生まれながらにしてある程度の免疫を受け継いで病気を防いでいるのです。これを「移行免疫」といいます。
移行免疫が効いている期間は病気に対する抵抗力を持っています。しかし、この移行免疫はワクチンの効果も打ち消してしまいます。移行免疫は長いもので生後100日まで持続する犬が多いことがわかっています。
そうすると、生後100日以降にワクチンを接種すればいいことになります。しかし、中には生後45日で移行免疫がなくなってしまう犬もいるのです。
この場合、生後100日までワクチンを打たないでいると移行免疫が切れてからワクチンを打つまでの期間、全くの無防備状態となり非常に危険です。そこで、数回に分けてワクチンの接種を行うわけです。
【ワクチンプログラムの一例】
子犬は5回接種が理想のワクチンプログラムだと言われています。しかし、5回も接種するとなると、費用も手間もかなりの負担となってきます。そこでもう少し接種回数を少なくして、かつ効果的なプログラムをご紹介します。
推奨ワクチンプログラムの一例(3回接種)
<ワクチン回数・・・接種/時期>
初回・・・4種混合/生後 6〜8週齢
2回目・・・7or8種混合/生後 9〜12週齢
3回目・・・パルボウィルスのみor 8種混合/生後 14週齢以降
※ 忘れないように月単位で接種する場合、生後2ヶ月でスタートし、3・4ヶ月にそれぞれ追加接種となります。
※ この推奨プログラムでは、一般的な8種混合までを紹介しています。
3.ワクチン接種と免疫力
前述のようなプログラムで接種していくと、3回の接種で済みます。
ただし、このプログラムを行っても100%安全ではありません。最後のワクチンを打ってから2週間(移行免疫がワクチンを打ち消しても病気の感染は防御できない期間)は感染を避けるため外に出すことは控えましょう。
????
<対処法>
(1) できる限り他の犬との接触を避けること
(2) 他の犬が排泄した可能性のある場所には人も犬も近づかないこと
(ワクチン接種を毎年きちんとしている犬との接触は問題ありません)
生後3ヶ月までは(行動学的に言うと)子犬の社会化期と呼ばれる重要な時期で、本来であれば他の犬と積極的に遊ばせたいところです。しかし病気の伝染も恐いですよね。
そこで、2回以上ワクチンを打っていて、外出しない子犬だけを集めて、互いの犬と遊ばせたり、それぞれの飼主さんに触れることでたくさんの人間と接触する機会を作れればかなりいい体験になります(パピースクールなどと呼ばれます)。
家の中にケージで隔離して、子犬に触る前には人の手も消毒するなど徹底的にできる方は、生後14週以降に1度だけ打てば1回で済みますが、毎日の手間を考えればワクチンを打ったほうが確実です。また、四六時中、ケージの中で隔離された子犬は社会性が身につかなくなり、後々問題行動を引き起こしかねません。
【追加接種について】
せっかく接種したワクチンも、時間とともに抗体価(抗体がどれぐらい体内にあるかという数値)が低下してきます。
抗体価が病気の感染を防げなくなるレベルに低下する頃に、追加接種を行い再び抗体価を上昇させるわけです。
コアワクチンについては、従来は年1回の追加接種を勧めていた一方で、
感染防御できる抗体がどのくらいの期間持続するか?を米国で調査したところ、3年以上もつ個体が多いという結果が出ました。これにより、米国の獣医師会では子犬のときに3回、1年目に追加接種、その後は2-3年間隔での接種を推奨プログラムにしています。
混合ワクチンはコアワクチン以外の病気も入っているので毎年接種が日本では多いのですが、都会の病院では1年間隔での接種をする病院も増えてきました。
しかし、犬の免疫力の個体差により3年程効果が持続するものもあれば、6ヶ月程で効果が消えてしまう場合もあります。さらに飼育環境や室内/室外飼い、気候などで接種すべきワクチンの種類、頻度も変わってきます。
ワクチンを追加接種する頻度については、必ずかかりつけの獣医師さんに相談し、ワンちゃんにあった方法を取るようにしてください。
4.ワクチンの副作用
他の注射と同じでワクチンにも副作用の可能性があります。
(1) 急性アナフィラキシー
注射後、数分でショック状態に陥り、死亡する例が数万頭に1頭くらいの確率であります(これはワクチンに限らず全ての薬であります)。注射して3〜5分後に吐き気がしたり、虚脱状態となり、立てなくなってしまいます。緊急対処としてエピネフリン、抗ヒスタミン剤、ステロイドを注射します。これで多くの場合は数時間で回復します。いかに早くこれらの処置を行うかが大事で、早急に処置をしないと生命に関わります。
(2) 遅延型アレルギー
ダックスフンドに多いのですが、ワクチンに含まれる成分のいずれかにアレルギー反応を起こすことがあります。体をかゆがったり、浮腫といって顔が腫れてしまったり、じんましんのような斑点が体にできる等の症状がでます。このような症状は通常、次の日には消えますが、あまりひどいときには病院に連絡してください(症状を抑える注射があります)。遅延型アレルギーの症状が出た場合は、追加接種のワクチンのメーカーやワクチンの数を変更します。
(3) 発熱
生ワクチンタイプでは病原性を失くしたウィルスを体で一度増殖させますので、発熱や食欲減退を起こすことが多いです。吐き気を伴うこともまれにありますが、これらの症状は正常な生体の反応ですから、あまり気にしなくても大丈夫です。
(4) 潜伏感染の発症
すでに何らかのウィルスに感染しているが、症状はまだ出ないという状況のときにワクチン接種によって病原ウィルスが暴れだすことがあります。
最後に…
ワクチンのしくみや「混合ワクチン」の種類、副作用などについてご紹介しました。ワクチンは犬の病気を防ぐためにはとても有効な手段ですが、接種の方法には諸説あり、一概には言えません。この機会にワクチンについてよく考え、愛犬の健康に役立てましょう。