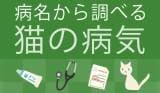感染経路
感染している猫の血液中に存在するウイルスは唾液や涙、糞便に排泄されます。そのためケンカによる咬傷、多頭飼育の環境ではネコ同士の舐め合い、トイレの共有などにより口や鼻からウイルスが体の中に入ることで感染が成立します。
感染後の経過
- <急性期>
- 侵入したウイルスは体内の様々な器官に運ばれ、造血器官である骨髄まで達し、そこで増殖します。感染成立後4〜8週間ほどでウイルス検査が陽性になります(急性期)。
- <回復、または持続感染期>
- 急性期後はウイルスが体内から排除される(回復)か、無症状であるにもかかわらずウイルス検査で陽性を示す(持続感染)、の2パターンに別れます。これは年齢による免疫力の違いによるもので、幼若なネコの方が持続感染になりやすいようです。
持続感染の場合、ウイルスは体内に居座り続け、その後、様々な病気を発症します。
猫白血病ウイルスが人の白血病の原因となる「ヒト成人T細胞白血病ウィルス」に似ているために白血病ウィルスと呼ばれます。実際には白血病よりも悪性リンパ腫を発症する場合が多いです。
症状
- <急性期>
- 発熱や元気消失、リンパ節腫大、白血球減少、血小板減少、貧血など。
- <持続感染期>
- 発症する病気により症状は様々です。血液疾患、免疫介在性疾患、口内炎、二次感染などが単独で、もしくは複数見られます。その後、様々な腫瘍を発症して死に至ります。腫瘍の発生は成猫では感染後3年が平均ですが、中にはウィルスを持ちながら10年以上生存する例もあります。
白血病陽性の親猫から産まれた子猫は1年以内に発症します。
診断
血液検査:血液中のウイルスを検査キットにより検出します。感染後4〜8週間経たないと検出はできません。
治療
感染の極初期にインターフェロンの連続投与により回復する例もありますが、現在、決定的なウィルス排除の方法はありません。
腫瘍が発生した時点で、その腫瘍に見合った治療が行われます。発症する病気の多くはリンパ種や白血病ですから抗癌剤で効果が見られます。リンパ腺の腫瘍の場合は抗癌剤投与で1年以上の生存を目標に治療します。ステロイドのみでも一時軽快しますが多くは2〜3ヶ月の命となります。
予防
ウイルスは猫の体外では不安定で、熱や消毒剤、太陽光線でも感染性を失います。
一番有効な予防法は家から猫を出さず、感染源と接触させないことです。多くの場合、猫同士のケンカで感染すると思われ、外出する猫は注意が必要です。一番感染率が高いのはケンカの多い未去勢のオス猫です。
ワクチン接種という方法もありますが、100%効果があるとは言い切れません。