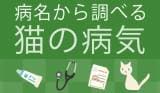原因
原因ははっきりとはわかっていませんが、アレルギー(ハウスダスト、ノミの咬傷、蚊の刺咬、食物などによる)、寄生虫、細菌感染、遺伝などが関係していると考えられます。また、猫がざらざらした舌で体を舐めすぎることに関係があるようです。
症状
- 1.無痛性潰瘍
- 上唇(犬歯が当たるところ)がえぐれて盛り上がる症状が見られます。また口の中の粘膜、下唇、皮膚などにも発生します。初めは赤く盛り上がり、さらに膨らんで中心が白っぽくなります。無痛性潰瘍には痒みも痛みもありません。
- 2.好酸球性プラーク
- 腹部、内股、後肢、首などにぼこぼこができ、その周辺が脱毛した状態となります。激しい痒みがあり、猫がざらざらした舌で舐め続けることによりバリカンで刈ったように毛が無くなってしまいます。さらに舐め続けると皮膚まで剥ぎ取られたようになり真っ赤な肉が見えるような状態にまで進行します。
- 3.好酸球性肉芽腫(線状肉芽種)
診断
通常、診断には飼い主からの情報と猫の身体検査でわかりますが、
・皮膚のソウハ検査(症状の出ている部分をひっかいて細胞を採り顕微鏡でみる)
・スタンプ検査(症状の出ている部分にスライドグラスを押しあて細胞を採って顕微鏡でみる)
・真菌培養(カビではないことを確認するため)
・血液検査(白血球の一種である好酸球が増えていることがあるため)
なども行うことがあります。
治療
皮膚炎に対する治療としてステロイドが使用されますが、寄生虫が原因の場合は駆虫薬、細菌感染が原因の場合は抗生物質なども使われることがあります。
しかしアレルギーが関係している場合、アレルギーの原因を特定するのは難しく、再発が多い傾向にあります。