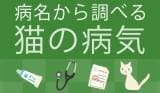原因
次の三つのいずれかが原因で起こります。
- 1.成長期にカルシウムが不足する
- ご飯と味噌汁などいわゆるネコマンマを主食としているとカルシウムが不足し、血液中のカルシウムが足りなくなるため、骨からカルシウムを放出して補おうとします。骨はもろくなり骨折を繰り返すため、骨が変形します。
しかし、成長期にカルシウムを過剰に摂取すると逆に骨がもろくなってしまいます。健康な猫にカルシウム製剤を与えるのはやめましょう。 - 2.カルシウムは足りているがリンを過剰摂取してしまう
- 魚の血合いの部分だけを材料にした粗悪なキャットフードを食べ続けたことが原因となる場合が多いです。カルシウムが足りているだけでは不十分で、カルシウムとリン、マグネシウムのバランスが適性であることが重要です。
- 3.光に当たらずビタミンD不足になる
- カルシウムの吸収にはアルブミン(蛋白質の一種)やビタミンDも必要です。光に当たらないと猫はビタミンDを摂取できません。
症状
手足や胴が寸足らずで、動きが鈍く痛みを伴うことがあります。また、元気消沈、背骨の変形、全身の筋肉の萎縮、虚弱、膀胱結石などがみられることがあります。虚弱の程度はさまざまですが、通常は軽度です。
骨折しやすく、背骨の変形から神経の麻痺が起こり、高齢になると高い確率で便秘になります。
これらの多くの症状は、飼い主は気付かず、動物病院で健康診断を受けた時に初めて気付くことが多いようです。
カルシウム不足はイライラの原因だと人間では言われますが、この病気をもつ猫は性格がきつくなる場合があります。
診断
通常は見た目だけで診断ができ、補助的にレントゲン診断をします。「ノートルダムのせむし男」のような感じの猫になります。歩行も地を這うような昆虫を連想させる特徴ある歩き方をします。
治療
栄養バランスのとれたキャットフードを与えることにより症状の改善が認められます。補助的にビタミンDやカルシウム製剤を与えます。生後2ヶ月くらいまでの猫は完治する事が多いですが、背骨の骨折を伴う場合は後遺症として跛行(はこう・足を引きずって歩くこと)や便秘などを伴う事があります。便秘については緩下剤の使用、治療用のキャットフードなどで対処可能です。