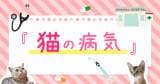猫のアレルギー
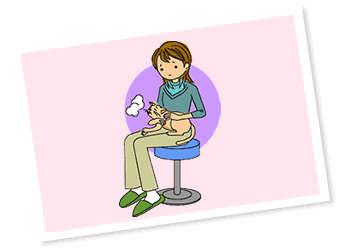
異物が体内に侵入した場合、免疫系統が抗体を作って異物を攻撃したり、
ある種の白血球が異物そのものを食べてしまったりして身体を守っています。
これら免疫系統が過剰に働きすぎて様々な障害を起こす疾患をアレルギーと呼んでいます。
今回はそんなアレルギーについてのお話です。
1.アレルギーの起こる仕組み
免疫系統がつくる抗体とは、外部からの異物に対し、自己防衛のために生体中の白血球が作る物質のことです。
一般的に私たちがアレルギーと呼ぶのは「スギ花粉症」や「カニやサバなどを食べたらジンマシンが出た」というものを指すことが多いです。猫でも同様に「皮膚を痒がる」「耳が赤くなる」「背中に湿疹が出る」といった症状で病院に行ったところ、アレルギーと診断された人は多いことでしょう。
このタイプのアレルギーは1型アレルギーと呼ばれます。他に2−4型まで全部で4種類あるのですが、我々が普段接するものは多くがこの1型ですから、まずはこのタイプに限って話をすすめたいと思います。
【アレルギーの起こる仕組み】
食物では大変多く見られる小麦のアレルギーを例に取ります。
(1)1回目の抗原摂取
(抗原とはアレルギーの起因物質のことで、アレルゲンともいいます)
飼い主がクッキーのかけらを猫に与えたとしましょう。
小麦の蛋白の主成分グルテンが体内に入ります。通常蛋白は腸内でアミノ酸に分解されてから吸収されますが、下痢などをして腸の粘膜が荒れていたりすると大きな蛋白のまま体内に吸収されてしまい、アレルギーの原因になりやすいと言われています。
異物であるグルテンをマクロファージという食細胞がキャッチして「異物が入って来たぞ」という情報を伝達役のヘルパーT細胞を経てBリンパ球に伝達します。
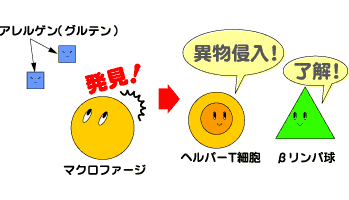
Bリンパ球はその情報によりIgE(免疫グロブリン)を造ります。産生されたグルテンIgE(グルテンに結合する免疫グロブリン)は体内に散らばり肥満細胞に付着します。つまり、次に同じ異物が入ってきた場合、同じ経路をたどってIgEを作るよりも、あらかじめ局所に散っておき、速やかに外敵をやっつける準備をするためです。この段階ではまだ症状は出ません。
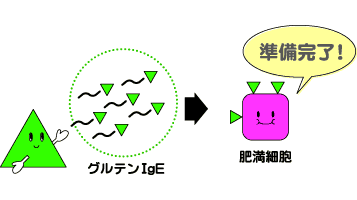
(2)2回目の抗原摂取
数週間後、お母さんがショートケーキを一口だけ猫に与えたとします。ケーキは小麦でできていますから2回目の抗原摂取になります。
肥満細胞に付着していたIgEと小麦のグルテン蛋白が結合して抗原抗体複合体になります。
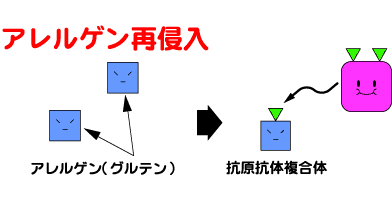
これがスイッチとなり肥満細胞から化学物質(炎症性メディエーターなどと呼ばれるヒスタミン、セロトニン、ロイコトエリンなど)が放出されます。
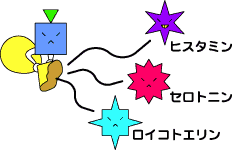
これらの化学物質の作用としては血管拡張、分泌亢進(分泌が高まる)、平滑筋と呼ばれる内臓器官や血管の筋肉が収縮するなどがあります。これらが激しく起こるために皮膚が赤く腫れたり、痒みが生じたりするわけです。
1型アレルギーは即時型アレルギーとも呼ばれ、通常は食後数時間で痒みが出てきます。激しいものでは顔面がぱんぱんに腫れることも珍しくはありません。
2.ワクチンによるアレルギー
猫ではワクチンによるアレルギーも見られます。アレルギーといえど、注射によるアレルギーは軽視できません。気道の浮腫(むくみ)が激しく生じたり、肺血管から水分が過剰に漏れ出たりすると窒息死する可能性もあります(滅多にありませんが)。
ワクチン注射の他、ハチに刺されてもアレルギー症状が出る場合があります。
注射やハチによるアレルギーは刺して3〜5分ほどで急激に現れる場合があります。この反応はアナフィラキシーショックという別名が付いています。この場合は痒みや腫れといったものではなく、血管の拡張が過度に進み血圧が急激に低下するものです。嘔吐や虚脱、粘膜が真っ白になるなどの症状が出ます。このタイプのアレルギーは非常に危険で早急に血圧を維持するなどの対処をとらないと生命に関わります(この症例も滅多にありませんが、1万頭注射したうち1〜2頭はあると思われます)。
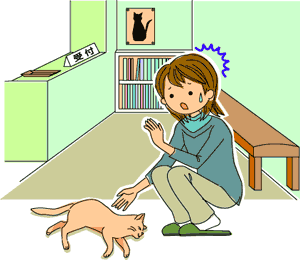
通常、動物病院での注射が終わって待合室で会計を待っているくらいの時間に症状が出ます。アナフィラキシーショックが起きた場合、いちいち注射アンプルを割って、希釈してから注射していては時間のロスになりますので、あらかじめ注射器にアナフィラキシーショック用の薬剤を入れて冷暗所に保存しておいて、ショック症状が起きたら瞬時に注射できるようにしている病院もあります。そのつど作る場合と比べて2分ほどしか時間の短縮になりませんが、その数分が命の分かれ目になることもあるのです。
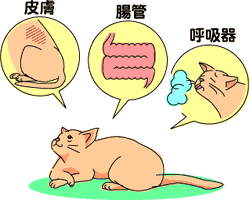
<アレルギーは皮膚の疾患だけではない>
アレルギー性呼吸器疾患
ほとんどのアレルギーの症例は皮膚疾患で来院しますが、実はそれだけではありません。
1型アレルギーの標的臓器は皮膚、腸管、呼吸器なので、下痢の原因が実はアレルギー性の腸炎という猫も実際よく見られます。グルテンアレルギーの場合は小麦が入ってさえいればなんでも反応しますので、かっぱえびせんをひとかけ食べただけでも重度の下痢になったりすることもあります。
また、猫では好酸球性肺炎というアレルギー性呼吸器疾患になることもあります。

3.アレルギーの原因物質を特定するには?
(1)血液検査
アレルゲン(アレルギーの起因物質)を調べるための血液検査があります。これは血液中のIgE(免疫グロブリン)を測定するものが多く、項目は36種類〜100種類ほどまで検査できます。しかし、検査項目数が多いため大変高額な検査になり、最低でも2万円はかかります。また、検査結果の感受性、特異性ともに低いため、結果が必ずしも正解ではない場合が多く、参考程度にしかなりません。検査結果が陰性だからといって必ずしも大丈夫とは言えないし、陽性と出たけれども大丈夫という場合があります。
また、アレルゲンになる可能性のある物質は数百万もの数があるとも言われていますが、それに対して検査できる数はごくわずかです。愛猫のアレルゲンである物質が、検査した数十の項目のうちに入っているとも限りません。
(2)スクラッチテスト・パッチテスト
スクラッチテストやパッチテストという、毛を刈って皮膚に直接抗原を接種して腫れ具合で鑑別する検査があります。こちらの方が精度は高いです。しかし、検査キットが市販ではありませんので、この検査を行っている病院はごくわずかです。
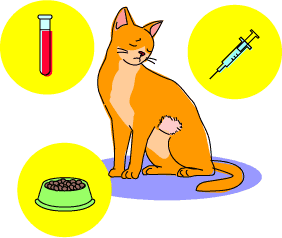
(3)アレルギー専用食を試してみる
食事性のアレルギーに関してはアレルギー専用食(アレルギーの原因となる食材が入っていないもの)だけを2ヶ月間与え、それで症状が軽快したならば食事性アレルギーと診断できます。その後怪しいと思われる食材を一つずつ与えていくと安価かつ正確に食事性アレルギーの原因を診断できることがあります。
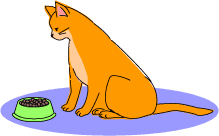
4.アレルギーの治療と予防
【アレルギー専用食の意味】
「アレルギーと診断されたのでアレルギー専用食に替えたけれど、アレルギーが治らない」という飼い主さんが多くいます。多くの人はアレルギー専用食を食べると(食事性の)アレルギーが治ると思っているようですが、そうではありません。ちょっと難解かもしれませんが。
アレルギー専用食は、それを食べたからといって痒みが軽くなるというものではありません。アレルギーの原因になりそうなたんぱく質(たとえば鶏肉等)を含んでいないというだけです。普通の猫が食べたことがないと思われる材料(ラム肉等)でできています。ラム肉を食べた事が無い猫は、ラム肉を使ったキャットフードを食べてもアレルギーは発症しない、というわけです。
しかし、せっかく猫が食べたことの無い材料で作ったキャットフードでアレルギーが起きないようにしているのに、おやつが原因でアレルギーを起こしてしまう場合があります。アレルギー専用食は、その専用食と水以外は一切与えないというのが前提です。ささみなどのおやつを与えながらアレルギー専用食を食べさせても、なんの効果もありません。
また、一度摂取した食事性のアレルゲンは1〜2ヶ月の間痒みを発症させるので、食事療法が無効かどうかは2ヶ月間の観察が必要です。

【アレルギーの治療法】
(1)アレルゲンの除去
アレルギーの原因であるアレルゲンを除去するのが理想です。
猫のアレルギーの原因はノミが一番多く、アレルギーの猫の7割はノミアレルギー性皮膚炎ではないかとの意見もあります。この場合、ノミの除去を行うと症状は改善します。
また、アレルギーの原因が一つではなく何種類かが混合していて、症状が悪化していることがあります。例えば、ハウスダスト、ノミ、鶏肉、スギ花粉に対して痒みが出る、という具合です。この場合、ハウスダストや花粉は除去できませんが、ノミの除去を行い、食事をアレルギー専用食にすることで、アレルギー症状は(完全に止められはしなくても)症状の改善は見込めます。
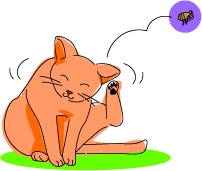
(2)内科的治療
薬で症状を抑える方法が一般的ですが、免疫を抑える薬を使用して一時的に止めることしかできません。薬を投与している間しか効果が出ないので、薬が切れた後、また痒みがでてくるのが普通です。人間では抗ヒスタミン剤が効果的ですが、犬や猫にはこの薬がほとんど効果が見られず、副腎皮質ホルモン(ステロイド)が治療のメインになります。
猫はステロイドに対する抵抗が大変強く、ステロイドによる副作用が起きることはめったにありません。ですので、持続性のステロイド注射が治療に用いられることが多いです。一回の注射で2週間ほど効果は持続しますので、この注射を1〜数ヶ月に1本注射することで多くのアレルギーはコントロール可能です。
【ノミアレルギーの予防法】
ノミによるアレルギーを予防するには、ノミが猫に寄生しないようにすることが一番大切です。ノミの予防には、「ノミとり首輪」「スポットタイプ(滴下型)」などの医薬品・市販品が効果的です。
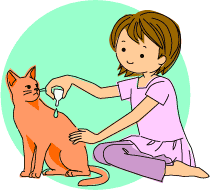
【食事性アレルギーの予防法】
(1)なるべく単一の食事を与える
通常アレルギーの症状が出てくるのは1歳前後からです。なるべく単一の食事にしておくと、アレルギーの原因を診断するのが容易になります。人間の食べ物をいろいろもらっている場合、摂取するたんぱく質の数が多くなるので診断も難しくなる上、複数のアレルギーを持つようになる可能性もあります。
(2)下痢をしたら絶食する
下痢時に食べた物が食事性アレルギーになる場合が多いので、猫が下痢をした時には絶食するか、たんぱく質の摂取を制限します。
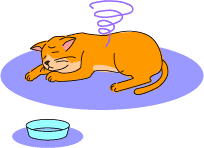
最後に…
今現在はアレルギーでない愛猫も、将来アレルギーを発症する可能性はあるのです。日頃からノミの予防をきちんと行いましょう。また、愛猫の食事には十分注意し、人間の食事やおやつなどを安易に与えたりしないようにしましょう。