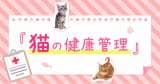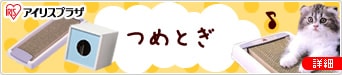猫の栄養学(2)塩分について
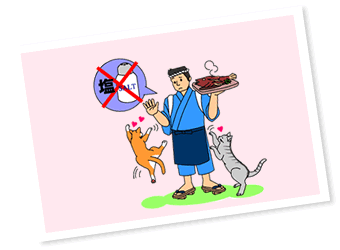
塩分は人間の身体に必要だということ、
塩分の過剰摂取は血圧の上昇をまねくなど
身体に良くないというのもなんとなく知っている飼い主さんも多いはず。
では、猫ではどうなのでしょう?
「猫に人間と同じ食事を与えてはいけない。人間の食事には塩分が多いから」
という話は良く聞きますが、その真相は…。
1.塩分の役割
そもそも、なぜ塩分(ナトリウム)が必要なのでしょうか。
「血液を舐めるとしょっぱいから血液には塩分が入っている。だから塩分が必要なんだろう」という考えも、まぁハズレではないです。
<塩分の役割その1>細胞の電気情報伝達の働き
通常、細胞の内部にはカリウムイオンが、細胞の外(血液)にはナトリウムイオンが多い状態になっていて、細胞膜がこの2つを仕切っています。細胞膜が一時的にイオンの透過性を変化させてナトリウムを細胞の内部へ、カリウムを外へと逆転させることにより電流を起こして情報の伝達を行います。微細な電流のために細胞外液のナトリウムイオンとカリウムイオンは常に一定のレベルに保たれなくては電流の発生がうまくいかず神経の情報伝達や心臓の収縮などが出来なくなってしまいます。塩分はナトリウムの濃度を維持する為、すなわち細胞の電気情報伝達のために必要なわけです。この、細胞の電気情報伝達が行われなくなると、生物は生きていけません。ナトリウムとカリウムは、それほど重要な成分なのです。
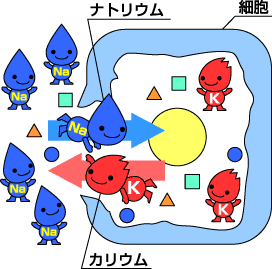
<塩分の役割その2>浸透圧の調整
もう一つ重要な役割が浸透圧の調整です。浸透圧が一定になっていないと細胞はしぼんでしまったり水膨れになったりします。
水中毒という変わった病気があります。一度に多量の水を飲むと、血液の浸透圧が低下し、その結果として赤血球が膨らんでパンパンになりパンクしてしまい溶血性貧血を起こす、というものです。この時に同時に塩分を摂取するとナトリウムが浸透圧を調整してくれるので赤血球の破壊は起きません。血液の浸透圧は水の量とナトリウムで調整されています。
2.塩分の過剰摂取
塩分の過剰摂取→血圧の上昇→腎臓に負担
塩分をたくさんとりすぎると塩化ナトリウムとして腸からすみやかに吸収されて細胞外液(血液)中のナトリウムの濃度が上昇します。ナトリウムイオンが多すぎると電流の発生が正常にいきません。そこで濃度を下げるために水で薄める必要がでてきます。しょっぱい物を食べると喉が渇くのはこのためです。塩分を多く摂れば、常にからだにたくさんの水を保持してナトリウムの濃度を一定に保たなくてはいけません。多くの水を蓄えるということは血管内部の液体の量が上昇するということで、これは血圧の上昇を意味します。さらに血液を送り出すポンプである心臓とナトリウムの排泄を行う腎臓に過大な負担を強いることになります。
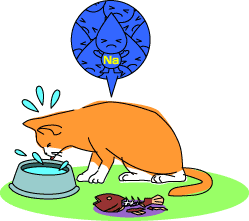
カリウムが高くなるとさらに事は重大です。血液中のナトリウムイオンの濃度が140前後なのに対してカリウムは4前後とかなり低い値に保たれています。これが倍の8くらいになると細胞の電流が止まってしまいます。ということは心臓が止まってしまい、即、死に繋がります。
ただ、ナトリウムと違ってカリウムは、過剰な分は体に吸収されません。カリウムをたくさん含む食べ物を多量に摂取したところで何ら問題はおきません。カリウムの値が高くなるのは病気の時だけと考えて良いでしょう。
猫カリウムの値が高くなる病気
・ 尿が出なくなった時
・ 糖尿病
・ 細胞が壊死した時(猫の心筋症)
3.人間より塩分摂取が低い理由
人ではナトリウム(塩分)の排泄方法として汗がありますが、猫は汗をかきません。ナトリウムの消費量が少なければ摂取する量も少なくてすみます。
そもそも野生の動物は食べ物に味付けをして食べるということをするわけがありません。人は「塩味をつけるとおいしさが増す」というのを経験的に知っているので味付けをするのですが、それを動物にも当てはめる必要はありません。(もっとも、動物でも塩分の濃い味付けの方がおいしく感じるようではあります)
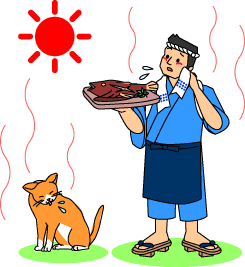
4.塩分が多く含まれる食べ物
蒲鉾やソーセージ、ハムなどの人間用の加工食品はもちろん、(猫用と謳っていても)ジャーキーなどのおやつ類もかなりの高塩分なので与え過ぎないようにしましょう。
化学調味料にも気を付けましょう。化学調味料のうま味成分で使われているグルタミン酸ナトリウムは、ナトリウムの量が塩と同じくらい多いです。
市販のキャットフードでもかなり味付けの濃いものがありますので嗜好性の高いキャットフードには注意が必要な場合もあります。一部の尿結石専用フードにもナトリウムの成分が多いものがあります。
特に高塩分の食事を避けるべき病気
・ 心臓病
・ 腎臓病
最後に…
今回は塩分(ナトリウム)とカリウムについて詳しく見てきましたが、いかがでしたか?塩分は猫にとって大切な成分ですが、与えすぎると健康に良くありません。人間と同じ食事を与えることはもちろん、嗜好性だけを重視したキャットフードやおやつを与えることも避けましょう。