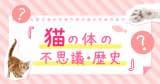猫の歴史
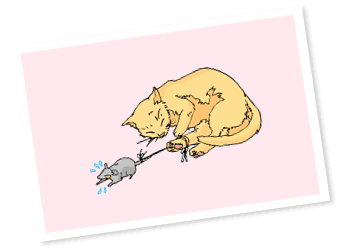
猫の起源や先祖って?
今回は現在でも残る、習慣などから見えてくる猫の歴史について、紐解いていきましょう。
◆INDEX◆
1.猫の起源
猫は、古代のミアキスと言う豹のような大きな動物が起源と言われています。
今から4000〜5000年前にエジプトから発生し、住み良い環境を求め分化して中東に行きました。
猫は古代エジプトでは絵画や壁画、又彫像等に表現されていました。
当時のお金持ちや、王様などが亡くなると何枚もの布で覆われたミイラにした後、一緒に棺に入れ大切に埋葬されました。

<エジプトから中国、ヨーロッパへ>
中東からインド・中国に渡り、穀類をネズミから守るための多く飼われるようになりました。
やがて猫はイタリアへ連れてこられました。ヨーロッパへ渡った猫の故郷もやはりエジプトであると言われています。
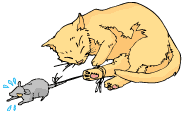
ペットとしての道のりは順調のようでしたが、中世ヨーロッパにおいて猫は宗教上の理由から猫への迫害がひどくなり、猫は魔女の使いをしていると考えられたようです。
1484年にローマ法王が猫及び猫を飼う人全てを処罰しました。フランスでも多くの猫が殺され暗黒の時代が続きます。
しかし猫が減ったヨーロッパの町ではドブネズミが大量発生し、その結果多くの伝染病が媒介されました。中でも、ペストの大流行で多くの人々が亡くなる中、ネズミを退治する猫が必要であると人々は認識せざるを得なかったようです。
17世紀の終わり頃に猫の名誉回復に大きく貢献する民話が誕生し、人気になりました。それはフランス文学界の代表作『長靴をはいた猫』です。
その民話をかわきりに18世紀には、猫が登場する文学作品が次々生まれてきて猫に対するヨーロッパの人々のイメージが良くなり、ペットとしての地位も向上していったのです。

2.日本での猫の歴史
やはり日本においての猫の歴史もはっきりした記録が残っているわけではないのですが、6世紀頃に、仏教の伝来と共に渡って来たものと考えられています。
仏教寺院ではネズミの被害を防ぐ為、猫を飼っていたものと思われます。古い書物や経典をネズミの被害から守る為に、猫を飼っていました。そのまま、船の中で、食料や、経典を守る為に海を渡ったと考えられているのです。

日本で飼い猫についての記述は平安時代初期まで遡ります。
宇多天皇記の中で宇多天皇が猫を大変可愛がり大切にしていた記述が残されています。当時真っ黒の猫が宮中で飼われている様子の記述の中で、おかゆを与えられたり音を立てず歩く姿を細やかに書かれています。
その後も、宮中の猫については『源氏物語』や『枕草子』でも記述がみられます。
鎌倉時代から一般の人達の間でもネズミ駆除の目的で猫が飼われるようになりました。
西洋の猫達に比べると幸せに過ごしていた猫ですが、江戸時代になると火鉢の火が猫の尾に引火して驚き走り回り大火を引き起こす事等もあり尾の短い猫が大切にされ始めました。
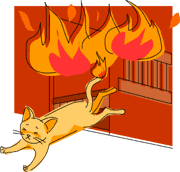
また、蛇を連想させる事から尾の長い猫が嫌われる傾向にあるようでした。猫の行動半径から同じような尾の短い猫が多くなったようです。
日本の伝説にも猫にまつわる怖い話はあります。老いた猫が若い娘を食い殺しその姿に化ける『化け猫』。猫が呪いや崇りなどの対象に扱われたりする事など。
洋の東西を問わず人間が猫に神秘的な力を感じるようですね。
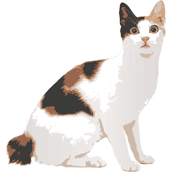
最後に…
いかがでしたか?今傍らに寝ている愛猫がそんな歴史を持った生き物だと思うと感慨深いものがありますね。