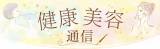冷えは万病の元
東洋医学には、「冷えは万病の元」という考え方があります。体が冷え、体温が下がると血流が悪くなります。すると全身に栄養や酸素が行き届きにくくなり、その結果病気に対する免疫力も下がってしまうのです。逆に、体温を上げると病気に対する免疫力も上がり、ガンにもなりにくいとされています。
女性特有の悩みとされてきた「冷え」ですが、最近では男性や子供にも多くみられます。しかし、冷えは自覚症状として現れにくいため、なかなか体が冷えていることには気付きにくいものです。
冷えを判断する方法
では、どういう状態を「体が冷えている」と判断するのでしょうか。まずは、手足が冷たい人。これはご自分ですぐに分かると思います。しかし、手足は温かい「隠れ冷え性」の人も増えています。
・体温が35度台の人、お腹が冷たい人
手足が冷えていなくても、体の内部が冷えていることがあります。
・体がむくみやすい人、汗っかきの人
体内に余分な水分がたまって冷えている可能性があります。
・暑がりの人
体が冷えているため、快適だと感じる温度が低い可能性があります。
また、外見や尿の色から判断する方法もあります。肌や唇、舌の色が白っぽい人、尿の色が透明・白っぽい人などは手足が冷えていなくても、体内が冷えていると考えられます。
体温別健康チェック
健康な人の体温は36.5度から37.0度だと言われています。ただ、発熱している時でない限り、体温の変化は自分では気付きにくいものです。ここでは、体温別に体の健康状態がどう変化するのか見てみましょう。
・28.0度以下:生命活動が停止した状態です。つまり人間は体温が28.0度以下では生きることができません。
・30.0度:生命が危険にさらされた状態です。意識を失い、昏睡状態になります。
・33.0度:重度の低体温症になった状態です。幻覚や錯乱などの意識障害が現れると言われています。
・35.0度:免疫力が下がり、病気になりやすい状態です。ガン細胞が最も活発に増殖する体温です。
・35.5度:自律神経失調症やアレルギー症状が出やすい状態です。
・36.5度〜37.0度:健康な状態です。免疫力が高く、ガンにもなりにくい体温です。
・37.0度以上:発熱している状態です。39.3度になるとガン細胞は死滅します。
いかがでしょうか。体温が低い状態が、病気になりやすいことがお分かりいただけると思います。
体が冷える5つの理由
現代日本人の体が冷えている理由。それは、生活習慣に大きな原因があると考えられます。今、手足が冷えているという実感のない方でも以下の5つに当てはまると感じる方は多いのではないでしょうか。
1. 運動不足
通勤通学に車や電車を使う、一日中パソコンの前で仕事をするなど、現代人の多くは体を動かす機会が減っています。体を動かさない結果、体温を産み出す筋肉が減り、血流が悪くなり、体温が下がってしまうのです。逆に、しっかり運動をして筋肉を使うと、血流は良くなり、体温も上がります。
2. ストレスが多い
体内の血流をコントロールしているのは自立神経です。 この自律神経には交感神経と副交感神経の二種類があります。 血管を収縮させるのが交感神経、血管を拡張させるのが副交感神経です。 私たちが仕事や人間関係でストレスを感じた時には、交感神経が優位な状態となります。 すると無意識のうちに血管が収縮してしまい、血流が悪くなってしまうのです。
3. 食生活の変化
食物には、体を冷やすものと体を温めるものがあります。 暖かい土地でよく育つもの、暖かい時期に旬を迎えるものは体の熱を冷まし、寒い土地でよく育つもの、寒い時期に旬を迎えるものは体を温めるのです。 しかし、現代では旬に関係なく、一年中食べたいものを手にいれることができます。 その結果、夏野菜のきゅうりやトマト、なすを冬に食べるなどして体を冷やしている人が多いのです。 また、生野菜の食べすぎ、冷たい飲み物の飲みすぎも胃腸を冷やすことにつながります。
4. エアコンの利用
冬だけでなく夏にも冷える人が増えたのは、エアコンの利用が増えたためでしょう。エアコンで部屋が冷えていると汗をかかず、体の体温調節機能は鈍くなります。また、屋内・屋外で温度差が大きいと、体温を調節する自立神経にも負担がかかってしまいます。
5. 入浴の仕方が悪い
体を温めるには、血行を良くして汗をかき、体内の余分な水分を排出することも必要です。汗をかきにくい冬は特に、しっかり湯船につかって汗をかくことが大切です。しかし、最近では冬でも入浴はシャワーですませるという人が増えています。シャワーを浴びるだけでは血行を促進できず、結果的に体を冷やすことにつながってしまいます。
体の冷えを取り、体温を上げるには、生活習慣を改善することが欠かせません。 次回は、体を温める方法を具体的にご紹介します。
参考文献
■五味パズルでマスター かんたん薬膳/武 鈴子 著 (講談社)
■元気とキレイの薬膳的暮らし/パン ウェイ 著 (PHP研究所)
■実践版 生姜力/石原 結實 著(主婦と生活社)
文:株式会社オールスパイス・藤野尚美
おすすめ商品
ほんのり甘く香ばしい♪体にうれしい、カロリーゼロ・カフェインゼロ!飲み切りやすい340mlタイプ