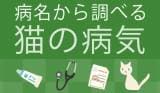トキソプラズマとは?
トキソプラズマは、経口摂取(口から入ること)により感染します。
トキソプラズマの生育には3つの段階があります。生育の段階によって、宿主の動物がどのように感染元になるかが違ってきます。
| オーシスト(卵のようなもの) | オーシストは小腸内で有性生殖により形成するため、ネコ科動物の糞便に出てきます。このため、糞便が感染元になる可能性があります(ただし、オーシストの排泄は感染から2〜3週間以内の期間です)。 |
| タキゾイト(オーシストの中の虫が卵から出て発育したもの) | 宿主の体内で形成されるため、感染した動物(例えばブタやネズミ)を食べることにより感染します。 |
| シスト(タキゾイトが集まって塊を形成したもの) |
症状
- <子猫の場合>
- 発熱、呼吸困難、嘔吐、粘血便、黄疸など様々な症状が現れ、ほとんどの場合死亡します(急性トキソプラズマ症)。
- <成猫の場合>
- ほとんどは無症状です。しかし衰弱した成猫では持続性の下痢、貧血や目に虹彩炎やブドウ膜炎(虹彩や、眼球をおおう脈絡幕の炎症)を起こし、目が濁ります。さらに中枢神経に障害が生じ、体の一部がマヒしたり、運動失調を起こすこともあります。このとき猫はまっすぐ歩けなくなり、ふらついたり同じところをぐるぐると回転することがあります(慢性トキソプラズマ症)。
診断
- A. 血液検査による抗体検査
- 間隔を1〜2週間空けて採血したペア血清(2回分の血清)を用いて、抗体の数値が上昇するかどうかを確認します。
- 1.2度とも陽性の場合
- トキソプラズマに感染済み。今後オーシストの再排泄の可能性はほとんどありません(この猫の糞が感染元になる可能性がほとんどないということです)。
- 2.2度とも陽性で抗体価が低値から高値になった場合(上昇)
- 現在進行中の可能性あり。オーシスト検出の可能性が高い。このタイプは要注意ですから妊婦との隔離が必要。
- 3.陰性から陽性になった場合(陽転)
- 急性期の可能性あり。オーシスト、タキゾイト、シストのどの段階で感染したかによりオーシスト排泄の開始時期が異なるため、必ずしも検出できるとは限りません。オーシストで感染したときは排泄がみられないことがあります。このタイプも一応隔離が必要。
- 4.2度とも陰性の場合
- まだ感染したことがない、または感染は経験しているがトキソプラズマが腸管の中しか生息しなかった、という2つの可能性かあります。現在の検査ではそのどちらかは鑑別することができません。感染未経験の場合は今後感染してオーシストを排泄する可能性があります。
- このように、血液検査の結果が陰性だからOK、陽性だから危険という単純な解釈ではありません。人が妊娠したことをきっかけに、飼い猫のトキソプラズマの検査をする人も多いのですが、血液検査が陽性だからといって猫を処分したりするのは早合点です(逆に陰性だから安心というものでもありません)。
- B. 糞便検査
- 糞便中のオーシストを検出します。
ただし、オーシストの排泄期間は2〜3週間で、ほとんどが無症状である上、慢性トキソプラズマ症の症状を示す頃には排泄が終わっているため、感染していても糞便からは検出できないことがあります。
治療
抗生物質や強化サルファ剤(サルファ剤と葉酸代謝阻害剤の合剤)の投与を行います。
予防
- <猫の予防策>
- 他の猫と接触させない、また猫に生肉を与えないこと。
- <人の予防策>
- 猫の糞便は速やかに片付ける、食器類やトイレの熱湯消毒をする(80℃では1分、100℃では数秒)。
また、加熱不十分な食肉は避けましょう。70℃で10分加熱するとオーシストは死滅します。人間への感染は、猫よりもブタの生食が原因になることの方が多いと思われます。