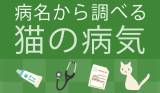肝臓の働き
正常な猫では、体内の脂肪組織、食べ物から摂取した脂肪や、肝臓の間で脂肪酸の循環がおこなわれており、そのバランスが重要になってきます。
過剰に餌を与えると、そのバランスが取れなくなってくるわけです。
食物からの脂肪は腸から吸収されるにあたって、脂肪酸に分解されます。その脂肪酸は血液中のアルブミンというたんぱく質によって、肝臓へと運搬されます。
そしてエネルギーとして消費されるか、トリグリセリド(TG)という形にかえられて、そのまま肝臓に蓄積されます。さらにそのTGはさらにアポプロテインという蛋白質と結合すると、リポプロテインとなりこの形だと再び血中へと送り出すことができます。
この摂取と消費の収支バランスが崩れると、肝細胞に過剰な脂肪が溜まっていくのです。
脂肪肝は肝硬変への入り口
末期にならないと症状はほとんど出ません。末期の脂肪肝では肝細胞が脂肪に置き換わってしまいついには消失してしまいます。肝細胞を支持する繊維状の細胞だけが取り残され肝臓は小さく萎縮して固くなっていきます。ここまでくると肝硬変と呼びます。肝硬変の猫肝臓が働かなくなる為、食欲がない、吐き気、下痢、黄疸によって皮膚の色が黄色いなどの症状が見られます。
食事を食べれない状態が数日続いても正常な肝臓を持っていればグリコーゲンを放出しますから血糖値は安定したままですが脂肪肝の肝臓はこれができません。
特に肥満の猫ではなんらかのきっかけで4−5日食べない状況がでると一気に黄疸が出て死亡することもあります。肝リピドーシスと呼ばれます。
肝機能障害が重篤になってくると、肝臓で尿素へと分解されるはずのアンモニアがそのまま血中にだされるため肝性脳症といった神経症状まで出てくる場合もあります。血液検査では、肝臓の障害の指標となるALT(GPT)、ALPなどの上昇、と肝臓で処理しきれなかったビリルビンの上昇がみられます。画像診断としてエコーが有効です。レントゲンでは脂肪肝の診断は不可です。
肝機能障害、リピドーシスの治療
肥満動物は貯蔵脂肪が大量にあるため食事を取らないとエネルギー源として体脂肪を使い始めます。そしてますます脂肪酸の収支バランスをくずしてしまします。
よってこの治療法としては点滴や強制給仕でエネルギーとしてグルコースをあたえ、体脂肪からの動員をストップするような支持療法が中心となります。
しかし、多くの肝硬変や猫での肝リピドーシスは治療への反応はあまり期待できません。肝硬変と診断を受けると余命はわずかです。
肝硬変の予防
脂肪肝、肝硬変などの病気になる傾向として、猫をとてもかわいがっており、欲しがるままに餌を与え続けてしまった飼い主さんに多いです。
症状が出てからでは手遅れになってしまっている場合も多く、自分が招いてしまった愛猫の不幸を後悔することになってしまいます。
さらに肥満は脂肪肝だけでなく、糖尿病や、足腰の病気、皮膚病、呼吸器疾患等も引き起こします。5年後、10年後のことも考えて、きちんとした食事管理をしていきましょう。
また脂肪肝だけでなんら無症状であり、肝硬変にまで至っていない状態だと回復は可能です。