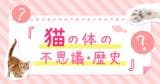猫の目の不思議

明るい時は縦に細くなり、暗い時はまんまるになる猫の瞳。
猫の目は暗い所でもよく見えると言われているけれど、どうしてなの?
また、猫が気をつけるべき目の病気って?
今回は、そんな猫の瞳について見ていきましょう。
1.猫の瞳が縦に閉じる不思議
猫の絵を描くと皆一様に目を縦に瞳を書きますね。ヘタな絵でも「あ、猫だね」とわかる特徴のひとつ。
子供の頃に読んだ忍者の本では「昔、猫の目で時間を予測した」なんてウソっぽいことがかいてあるのもありました。正午が線上に一番細くなり、未の刻(午後2時頃)と巳の刻(午前10時頃)はちょっと開いて辰の刻(午前8時頃)と申の刻(午後4時頃)は…。天気が悪ければあてにならないでしょうけど、猫の瞳は線のような細さからまん丸まで大変よく動きます。
真っ暗になったときに瞳は全開になりますが、人間と比較すると瞳がいかに大きく開いているかがわかるはずです。人でも瞳が大きく開けば美人に見えるといいますが、猫は倍ほど開きます。これはレンズの大きさが大きい為です。
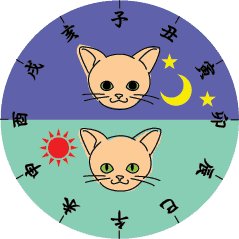
2.猫の目のしくみ1(猫のレンズ)
<猫のレンズは大きい>
光を集める水晶体の直径以上に瞳を開いても意味が無いので、人間の瞳は全開でもあまり大きくありません。そのため人の目は“白目”と呼ばれる強膜が外から露出して見えます。猫の目は普通は白目が見えません。眼球の大きさに対してそれだけレンズが大きいということです。また、頭の大きさに対しての眼球の直径もかなり大きいです。4kgほどの猫の眼球でも人の目と同じくらいのサイズがあります。体重100kgを越えるブタよりもむしろ猫の方が眼球の大きさは大きいくらいです。
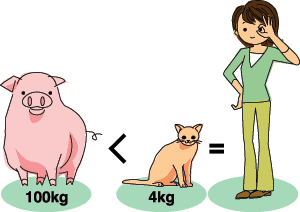
レンズが大きいということは多くの光を集められるので少ない光でもよく見えるということになります。
<猫のレンズは厚みがある>
さらに(通常のほ乳類と比較すると)レンズに厚みがあります。凸レンズの厚みが厚いということは集めた光が集中する焦点までの距離が短いということ。簡単に言えば、レンズと網膜の距離が短いのです。「光の強さは光源からの距離の2乗に反比例する」なんて高校の物理で習ったような記憶がありませんか。1mと2mの距離で明るさを測定すると距離が2倍になると明るさは4分の1、4倍になると16分の1。レンズから光を受ける場所は近いほど効率がいいわけです。
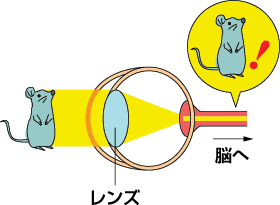
3.猫の目のしくみ2(猫の目)
<猫の目は光を感知する細胞が人間の6倍!>
光を集める仕組みはレンズだけではありません。網膜の細胞には棒細胞(光を感知する細胞)と円錐細胞(色を識別する細胞)があります。猫の網膜では解剖学的に言うと光を感知する細胞が人間の6倍で、逆に色を感知する細胞が6分の1と言われています(犬もだいたい一緒)。単純に考えれば暗いところでも6倍明るく見えるということ。そのかわり色はあんまりわからないということになります。以前はほとんどシロクロにしか見えないんだろうと言われていましたが、まるっきりのシロクロでもないようで青や緑は若干わかるようです。
<猫の目の奥に光を反射する鏡がある!>
さらにもう一つ少ない光でも見える仕組みがあります。暗闇で猫の目を懐中電灯で照らすとギラっと目が光ることがありますね。網膜のさらに奥に鏡のように光を反射する部分(輝膜や輝板と呼ばれます)があるのでギラギラ光って見えるのですが、一度網膜で感覚細胞を刺激して通り抜けた光をこの鏡で反射してもう一度感覚細胞を刺激してやるわけです。
猫の目って超高性能の暗視カメラになっているんですね。

<猫の目は前面にあるため距離感を得やすい!>
牛や馬などは体の横向きに目が付いています。広い死角を得るためにはこの位置でなくてはいけないのです。獲物に襲いかかるわけではないので正確な距離感覚はあまり必要ない、つまり両目で同じ物体を見る必要はないのです。これに対し、猫の目の位置は前方に向いています。両目で同一の物体を確認するためでこれは距離感を正確に掴むのに適しています。
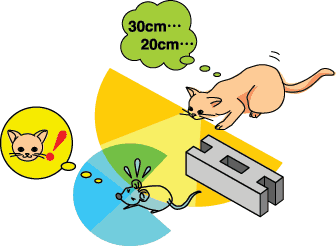
4.気を付けたい目の病気
猫の白内障は犬に比較して大変少なく、緑内障もまた少ないです。気をつけたい猫の目の病気は、ブドウ膜炎です。
ブドウ膜とは、瞳の周り(猫の場合、金色やブルーなどの部分=虹彩)とその周辺の組織(毛様体・脈絡膜)のことです。ブドウ膜炎とはブドウ膜の一部または全部に炎症が起こる病気です。
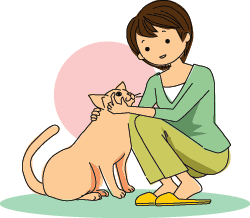
最後に…
猫の目は光を感知する能力に優れていて、超高性能の暗視カメラ並みであることがわかりました。普段は家の中で寝てばかりのように見える猫ですが、獲物を捕らえるために目の機能がとても発達していたのですね。意外な猫の素顔が見えた気がしませんか?
そんな猫にとって目はとても大切なもの。目ヤニが増えたり涙が止まらないなどの異常がないか、普段からよくチェックし、異常があればすぐ動物病院を受診しましょう。