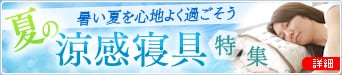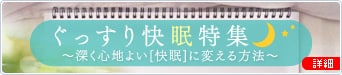本格的な夏到来。寝苦しい夜が続き、ついつい朝起きる時間が遅くなってはいませんか。また、学生の皆さんは夏休み。お子さんが目を覚ます時間も遅くなりがちですよね。
そんな季節だからこそ今回は、早起きできない原因を知り、「早寝早起き」の習慣を身に着けるコツを紹介します。
早起きできない原因とは?

そもそも、早起きできないのはなぜなのでしょうか。
1.睡眠時間が不足していませんか?
厚生労働省が推奨している睡眠時間は以下の通りです。(出典:厚生労働省 健康づくりのための睡眠指針 2014)
- 年代
- 睡眠時間
- 10歳代前半
- 8時間以上
- 〜25歳
- 7時間
- 〜45歳
- 6.5時間
- 〜65歳
- 6時間
個人差はありますが、睡眠は6〜8時間くらい必要といえます。あなたの睡眠時間は足りていますか?
2.休日に寝だめしていませんか?
平日の睡眠不足を補うため、休日などにまとめて寝る「寝だめ」をしていませんか。残念ですが「睡眠」は貯めることができません。
また、起床後に日光を浴びることで私たちの体内時計はリセットされます。そして眠りを促すメラトニンというホルモンは、日光を浴びてから約16時間後に出るようになります。
休日に遅い時間まで眠っていると、体内時計の調整やメラトニンの分泌が適切に行われないため、入眠困難や目覚めの悪さにつながります。
3.寝床に入ってからが長くありませんか?

近年、寝る直前までスマートフォンを見ている人が増えています。寝床に入ってからメールやゲームに熱中すると、興奮で目が覚めてしまいます。長時間の光の刺激もさらに覚醒を助長し、体内時計の狂いや入眠困難につながるので注意が必要です。
一方で高齢の方の場合、活動量の減少などによって若いころより必要な睡眠時間が少なくなります。そのような中、眠くないのに無理に眠ろうとするとかえって緊張を高め、寝付を悪くする場合があります。
また睡眠時間を必要以上に長く取ると、徐々に眠りが浅くなり夜中に目覚めるようになります。特に退職後に時間にゆとりができた場合などは、生活の変化がきっかけとなって、必要以上に長く寝床で過ごしてしまう傾向があります。
4.ストレスはありませんか?
心が疲れていると早起きが出来ないといわれています。仕事・子育て・私生活などのストレスが、起きようとする気持ちを妨げたり、眠りを浅くしたりします。また、ストレスが原因で深酒をし、朝起きられないという悪循環に陥ることもあります。
他にも、原因は様々ありますが「早起き」をするには、「良い睡眠」が大切です。
世代別 良い睡眠のとり方(出典:厚生労働省 健康づくりのための睡眠指針 2014)
学生世代

若い方は、休日の起床時間が平日より2〜3時間程度遅くなることが多くあります。 高校生では普段より3時間遅く起きるのを2日続けるだけで、体内時計が約45分も遅れることが分かっています。 こうした休日の起床時間の遅れは、これからの夏休みなどの後には特に大きく影響します。
お子さんがいるご家庭では、夏休みこそ規則正しい生活を続け、体内時計が狂うのを防ぎましょう。
社会人世代

仕事をしている方は、仕事や生活の都合で充分な睡眠がとれないことも多いでしょう。日中の活動に支障をきたすような眠気があるようであれば注意が必要です。そのような場合は、お昼休みなどを利用して、30分程度の短い昼寝をすることをおすすめします。短時間でも睡眠をとることで、作業効率の改善やミスの軽減、ストレス軽減につながります。
シニア世代

高齢になると、若年期よりも必要な睡眠時間が短くなります。例えば65歳の方は20代の方と比べ、必要な睡眠時間が1時間少なくなると考えられています。若い頃と同じように長い時間眠ろうとして寝床で過ごす時間が長くなると、かえって睡眠が浅くなり夜中に目覚めやすくなるなど熟睡感が得られません。
年齢に合った睡眠時間を理解して、就寝時間と起床時間を見直すことが大切です。日中眠くならないかも適切な睡眠時間を確保できているかの一つの目安になります。
また、日中に適度な運動を行うことで、覚醒と睡眠のリズムにメリハリがつき、短時間でも深く安定した睡眠が得られ、結果的に熟睡感の向上につながると考えられます。
良い睡眠と早起きのメリット
生活習慣病の予防につながる
睡眠時間が不足している人は、生活習慣病になる危険性が高いことがわかってきました。睡眠不足や不眠を解決することで、生活習慣病の発症を予防できるとされています。
ストレスが軽くなる
良い睡眠がとれていると日中の注意力や集中力が向上し、体の調子が良くなり活動意欲が高まります。反対に良い睡眠がとれていないと眠っても心身の回復感がなく、気持ちが重たく物事への関心がなくなり、好きだったことが楽しめないなどといった症状が発生します。
生活リズムが安定する
朝早く起きて太陽の光をしっかりと浴びることで、脳内の松果体という部分が刺激され、自然な眠りを誘うメラトニンというホルモンが適切な時間帯に分泌されます。また、早寝早起きのリズムが定着すると、時間的余裕が生まれ、心にも余裕が出るという好循環になります。
名経営者もみんな早起き!
少し話が逸れますが、世界的企業の経営者には早起きしている方が多いってご存知でしたか?その一例を紹介します。
- ティム・クック(アップルCEO)
- 4時半起床。部下にメールで指示、その後ジムで運動。
- ハワード・ショルツ(スターバックスCEO)
- 4時半起床。起きてまず妻にコーヒーを淹れ、6時前に出社。
- マーク・パーカー(ナイキCEO)
- 5時起床。1時間みっちり運動。
- 織田信長(戦国武将)
- 4時起床。片道4kmのコースを馬に乗り往復していたと伝えられています。往路で戦術を練り、復路で決断をしていたようです。
良い睡眠を得るために、マットレスにこだわりたい
ご存知ですか?1年間で寝返りする回数
1日平均20〜30回とされる「寝返り」は、1年で約7,300回にも達します。そんな「寝返り」は、睡眠において重要な役割を果たしていることが知られています。1回1回の寝返りをサポートすることが、毎日の快眠につながるのです。
寝返りがラクだと、眠りは深まる

寝返りは、睡眠中の身体の負担を和らげるために自然に行われる動きで、身体の同じ部分が圧迫され続け、血液循環が滞ることを防ぎます。また体温の調節や湿気の発散という役割もあります。
そんな、快眠に欠かせない寝返りで、筋力を使ってしまっては脳が覚醒しやすくなってしまいます。
また、マットレスや敷き布団が柔らかすぎると、腰部と背中が深く沈み込んでしまい、寝返りしにくいだけでなく腰痛の原因にもなります。逆に硬すぎると骨が 当たり痛みを感じ、血流が滞りやすくなり熟睡を妨げる原因となります。
理想的な寝姿が、熟睡につながる

アイリスオーヤマの『エアリーマットレス』は、3次元スプリングの高い反発力で寝返りをサポートし、寝返り時に身体にかかる負担を軽減。また、身体の沈み込みをあらゆる方向から支え、効果的に体圧を分散することで、理想的な寝姿勢を保ち、より深い眠りへとあなたを導きます。