地震対策についてアイリス暮らし便利ナビ会員さんにアンケートを実施しました。 今一度防災対策について考えてみませんか?また、近年増加しているゲリラ豪雨などの水害についてみなさんのアンケート結果とともに、 日頃備えておきたい対策をご紹介します。


地震対策について
![]() 現在地震対策はしていますか?
現在地震対策はしていますか?
回答人数:1,402人 対象:アイリス暮らし便利ナビ会員
2011年
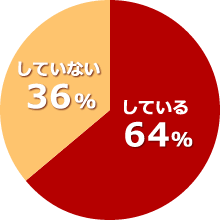
2014年
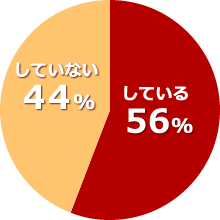
2014年の調査で地震対策をしている方は56%。
2011年の調査で地震対策をしていた方は64%と3年前に比べ8%減少していることがわかりました。
震災から約3年が経ち、東日本大震災直後よりも防災意識の薄れを感じます。
地震対策の減少傾向を食い止めるためには、やはり1年に一度でも見直しを行う必要が
あると思います。
では、実際行っている対策の中で、多い対策はどんなものがあるのでしょうか?
![]() 具体的に行っている防災対策は何ですか?(複数回答)
具体的に行っている防災対策は何ですか?(複数回答)
地震対策をしていると答えた方:623人
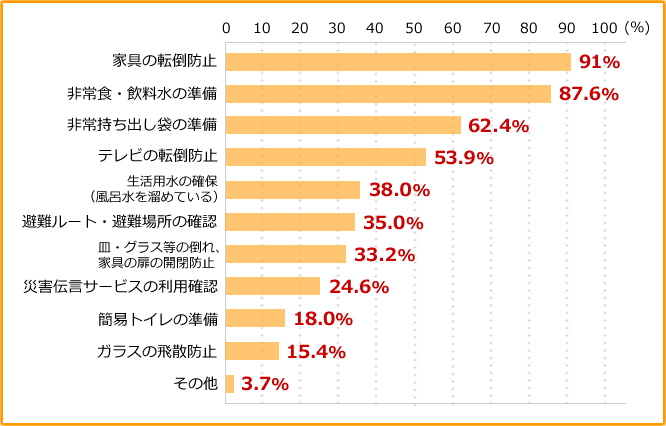
地震の経験を教訓に、家具の転倒防止や非常食・飲料水の準備などが多い結果となりました。
やはり日頃の備えなどが重要になっています。
みんなの対策
- 東北に親戚が沢山いるので、東北大震災の時に食料や日用品がなかなか確保できなくて困ったので、常に常備しておくように心がけています。準備するだけでなく、定期的に中身を確認して、保存食の賞味期限などを確認する様にもしています。ペットがいるので、猫ちゃん用の非常食なども用意してます。
- 東日本大地震の時に計画停電を経験して、非常用の電気の必要性と、全てを電気に頼ってはいけないという教訓を得ました。幸い我が家は、オール電化ではなく、水道は出て、プロパンガスのコンロでしたので煮炊きも出来ました。ただ季節が3月で少し肌寒い時期でしたので、電気を使う暖房器具しかなく寒い思いをしました。電気は大変便利ですが、全部頼ってしまうと自然災害の時には当てにはならないという事を学びました。
- 東日本大震災直後に防災用品を揃えるようになりました。よくテレビでやっている、非常食を普段の食事のローテーションに入れ、常に新しい非常食を準備するようにしています。
水害対策について
地球温暖化の影響で、気温が上昇し、熱帯夜(夜間の最低気温が25℃以上の夜)や猛暑日(1日の最高気温が35℃以上の日)が増えています。さらに、1日に降る雨の量が100ミリ以上というような大雨の日数が増える傾向にあります。 このような環境の変化の中、みなさんの水害に対する防災意識は高まっているのでしょうか?
![]() 昨年よりも台風・大雨などの防災の意識は高まりましたか?
昨年よりも台風・大雨などの防災の意識は高まりましたか?
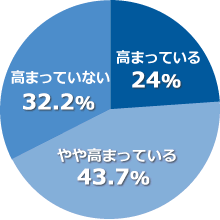
高まっている・やや高まっていると回答した方が、全体の67%となりました。 ゲリラ豪雨や台風などのニュースが報道されることが多いので意識が高まっているようです。
![]() 現在台風・大雨に対する対策はしていますか?
現在台風・大雨に対する対策はしていますか?
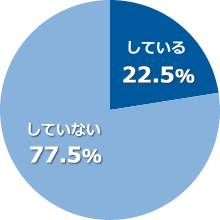
意識の高まりとは比例せず、対策をしている方はわずか22.5%と少ない結果に。
実際の対策はどのようにすればよいのでしょうか?
みんなの対策
- 我が家は地盤が低く、大雨が降ったら増水し床下浸水になりやすい為、大雨が降る際は車を高いところまで移動させたり、下水道のマンホールも増水してくるので、重石を乗せたりと準備万端にしてます。
- 床下浸水した時の水の速さで、増水してきてからでは間にあわないと思いました。 浸水は家の前からだけではなく、雨水の排水溝からも逆流し、あらゆる方向から浸水してきます。無駄でも土のうなどは情報を確認しながら用意しています。
- 床下浸水に10年ほど前になりましたが水はどこからでも入ってきますので防ぎようがなかったです。(排水溝など)ネズミや蛇(マムシ)なども泳いできたりしてとっても怖い思いをしました。土のう等は間に合わなかったです。(簡易土のうがあればいいなと思いました)
水害対策
具体的な物的対応よりも、まずは、住んでいる地域が被害が起こりやすい地域か確認する必要があります。
土地の歴史や特徴が地名に残されている場合もあります。
水のたまりやすい地名・・・カワチ(川内)、ナダ(灘)、ウシ(牛)、サワ(沢)、フカ・フケ(深)、リュウ(竜)などの場所は、現在でも水につかる可能性が高いといわれています。
地名が変わっている場合もあるので、図書館などで昔の地名を確認してヒントとして活用したいものです。
一方、先祖を祀る神社や仏閣は古くから水害を受けにくい場所を選んで建てられているようです。
※必ずしも地名によって水害を受けやすい地域とは限りません。
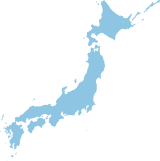
何よりも早めに対応することが大切です。気象情報をこまめにチェックして、雨量や警報を確認しましょう。 日頃から避難場所の確認を行い、速やかに避難できるように準備します。避難時は車ではなく徒歩で高台に避難しましょう。車が浸水したり、渋滞が 起こり逃げ遅れる可能性があります。また、気象庁から発令される避難勧告と避難指示の違いについて、きちんと理解しましょう。
避難勧告と避難指示の違い
避難勧告
その地域または土地、建物などに災害が発生する危険性がある場合に発令される。できるだけ避難を始めることが望まれている。できない場合には、その後の状況に応じてすみやかに避難ができる準備をしておくことが必要である。
避難指示
勧告より状況がさらに悪化し、避難すべき時機が切迫した場合や、災害が発生し、現場に残留者がある場合に発令される。危機が差し迫っているため、すみやかに安全な避難場所へ移動することが大切である。
命の危険が高い土砂災害は予兆を察知して、速やかに避難することが大切です。
- 山鳴りがする
- 雨が降り続いているのに川の水位が下がる
- 川の水が急に濁り、流木が混ざりはじめる
- 地面にひび割れができる
- 沢や井戸の水が濁る
- 斜面から水が吹き出す
- 小石がバラバラ落ちてくる

防災対策アイテム
家に浸水の危険が迫った場合、土のうやブルーシートを使用して、浸水を防ぎます。
床上浸水の場合、電化製品が水に濡れる可能性があり、水に濡れると使用できなくなるので、
早めに移動させることも大切です。
また、避難時にすぐに持ち出せる避難用持ち出し袋も準備しておきましょう。
-

緊急簡易土のう
-

ブルーシート
-

避難リュックセット
家族用15点 -

避難リュックセット
家族用22点 -

【静音&ハイパワータイプ】高圧洗浄機 FIN-901E/W
最後に・・・
いつまた未曾有の災害が起こるかわかりません。
一年に一度は、防災対策の見直しを行い、日頃の備えを行って災害に備えましょう。
参考資料:国土交通省HP、気象庁HP











