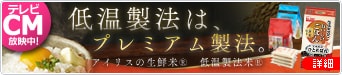わかっているようであやふやな部分も多い夏のお付き合いに関するマナー。
お中元、暑中見舞い、残暑見舞いの疑問をしっかり確認して夏のマナー美人を目指しましょう。
お中元ってどういうもの?
お中元の起源は、お盆の時期に、先祖への供物を実家に持ち寄ったことだといわれます。
現在のお中元は、仲人、上司、習い事の先生など、日頃お世話になっている方々に感謝の気持ちを伝える季節の贈り物となっています。
お中元を贈る時期は、7月初旬から中旬(15日)頃までが一般的ですが、関西や新潟等、旧盆の習慣がある地域では、8月初旬から中旬(15日)頃に贈る場合もあります。
お中元を贈る相手・金額相場は?
お中元は、どんな相手にいくらくらいの品物を贈るかが悩ましいところですが、まず、送る相手には決まりはありません。 ただし、お中元の贈答を禁止している場合もあるため、初めてお贈りする相手には、あらかじめ聞ける間柄の場合はそれとなく聞いておくといいでしょう。
会社の場合、社内のルールや慣習がある場合が多いので、まずは周囲に確認しましょう。
なお、喪中の方の場合も、お中元は感謝の気持ちを伝える贈り物なので、喪中に贈ってもかまいませんが、四十九日の忌明けを待ってからお贈りしましょう。
金額については、特にお世話になっている人には、3,000円〜1万円、取引先や勤務先の上司、仲人へは5,000円、親戚、知人、習い事の先生などへは3,000円〜5,000円というのが一般的です。 ご挨拶や心づけ程度の意味合いの場には、1,000〜2,000円が相場です。
お中元ののし・水引・表書きは?
基本としては、お中元をかしこまった相手に贈る場合や、直接持参して手渡しする場合には、より格の高い「外のし」をかけます。 贈る気持ちを強く主張したくないときや、宅配便などで送る場合には、箱に直接かける「内のし」を用います。 水引は紅白の蝶結びを使います。
表書きの上段には、「御中元」と書き、下段には苗字かフルネームを書きます。相手が目上の方であれば、「暑中お伺い」や「残暑お伺い」としましょう。
なお、喪中の方の場合は、紅白の水引を避けて、白無地の奉書紙を用います。
もし、お中元を贈るべき時期を逃してしまった場合、表書きは、立秋までなら「暑中見舞い」、立秋以降は「残暑見舞い」とします。
お中元に何を贈る?贈ってはいけないものは?
お中元の品物として多く選ばれているのは、ビール・ジュースなどの飲み物や、ゼリー・そうめん・海苔などの食品です。また、産地直送品も人気のギフトの一つです。
贈られる側としては、調味料や洗剤などの実用的な消耗品や、商品券やギフト券など自由に選べる物が好まれているという声も多くなっています。 金券を贈ることは、以前はお金を贈ることと同様で避けたほうがよいとされていましたが、時代が変われば文化も変化するようです。
ただし、贈らないほうがよいとされる物もあります。 例えば、弔事でよく贈られるお茶を贈るのはあまり縁起が良くないとされています。
また、目上の方に贈ることは失礼だとされているものもあります。 まずは靴や靴下・スリッパなどの足元に使うもの。これらは『踏みつける』を連想させるためです。また、筆記用具や時計などは『勤勉奨励』を連想させるため、贈るのは避けたほうがよいとされています。 同様に、先に紹介した金券を贈ることは目上の方には避けておくほうがよいでしょう。
ただし、最近では相手の好みを尊重して品物を選ぶ傾向があり、贈ってはいけないものにもあまりこだわらなくなっています。
お中元の送り状・挨拶状
送り状や挨拶状は品物よりも数日早く相手に届くようにするのがベストです。
ビジネスで関わる方や目上の方など改まった相手に書く場合には、正式な手紙の書き方に沿うのが一般的です。 「拝啓」「謹啓」などの頭語で書きはじめ、時候のあいさつと日頃の感謝を述べた後、品物の内容、贈った理由、発送日、到着予定日などを書き添えるのが良いでしょう。「敬具」「敬白」「かしこ」など、頭語と対になる結語で終わります。
親しい相手に書く場合は、形式にあまりこだわらず、素直な気持ちを込めた手紙にしましょう。
お中元の送り状例文
お中元を受け取ったら(お返し、お礼について)
基本的に、お中元にお返しは必要ありません。 ただし、品物が無事到着したことを知らせる意味でも、お礼を伝えるのがマナーです。
親しい間柄であれば、メールや電話で伝える方法もありますが、できればお礼状を書きたいものです。 長い文章を書く必要はありませんので、ハガキでもかまいません。
お礼状には、季節のあいさつ、相手の近況を尋ねる文章、品物へのお礼や日頃のお礼に加えて、相手の家族に対する心遣いを書き添え、結びのあいさつで締めくくります。
暑中見舞い・残暑見舞いの季節と書き方
最後に、お中元と同様に夏に欠かせないマナーとして、暑中見舞いと残暑見舞いについてご紹介します。
「暑中」は、二十四節気の「小暑(しょうしょ)」と「大暑(たいしょ)」にあたる期間で、暑中見舞いもこの間(7月7日頃から8月7日頃まで)に出しますが、本来は、大暑にあたる7月22日頃から立秋までに出すのが正式です。 立秋を過ぎた場合は、「残暑見舞い」として、8月末頃までに出しましょう。 暑中見舞いの書き方に堅苦しい決まりはありません。 季節のあいさつ(「暑中お見舞い申し上げます」等の決まり文句)」ではじめ、先方の安否を尋ねる文章や無事を祈る言葉、自身の近況を伝える文章を書いて、最後に日付を入れます。 日付の代わりに「○○年 盛夏(晩夏)」とするのも良いでしょう。目上の方に書く場合であっても、頭語や結語は要りません。